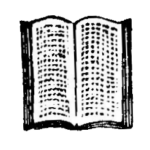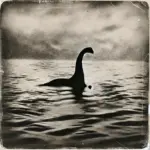インドの伝統、「ランボーグ米」が復活しています!
「Down to Earth(2025年2月1日号)」を読んでいたら、インド北部のウッタル・プラデーシュ州で、香り高い「ランボーグ米」を復活させようとしている記事を見つけました。この「ランボーグ米」は具体的な品種名がはっきりしないのですが、おそらく伝統的なインディカ米の一種で、バスマティ米やカランアマクのような香りの良いお米を指している可能性があります。我が家ではカレーが定番なので、インドのお米事情はとても気になります。
この取り組みの面白いところは、化学肥料を減らし、有機肥料や自然由来の資材を使う農法に切り替えている点です。カンプール・デハットやカンプール・ナガル地区の農家の方々が努力していて、驚くことにこれで「コスト削減」にもつながっているそうです。日本では「エコは高い」というイメージが強いのですが、昔は自然の肥料で農業をしていた時代もあるので、考えてみれば納得できます。土壌も健康になり、持続可能な農業への第一歩になっているのですね。
「グラスピー」をご存じですか?
もう一つ興味深いのが、「グラスピー」という豆の話題です。学名は「Lathyrus sativus」で、インドでは「ケサリダル」とも呼ばれるマメ科の植物です。乾燥に強くてやせた土地でも育ち、湿潤な環境でも問題なく、しかも収穫量が多いので、「貧者の豆」として食糧不足を救う可能性があります。
ただ、少し困った一面もあります。グラスピーを過剰に食べると、神経毒性のリスクがあるのです。そのため、1961年からインド政府は販売や貯蔵を禁止してきました。しかし最近では、マハラシュトラ州やチャッティースガル州、西ベンガル州などの一部地域で、この禁止が解除されています。2025年3月時点の情報によると、食糧問題を解決するために「忘れられた作物」を復活させようとする動きが広がっていて、グラスピーもその一つです。過剰摂取に気をつければ、未来の食卓を支える存在になるかもしれません。
在来種を守ることが大切です
最近、異常気象が続いていますね。そんな中で感じるのは、その土地に合った在来種を残すことの重要性です。ランボーグ米もグラスピーも、気候変動や干ばつに強いDNAを持っているので、少ない資源でもしっかり育ってくれます。
化学肥料や農薬で「とりあえず収穫できればいい」というやり方では、目の前の問題は解決しても、土壌が疲弊して長続きしません。地球に生かされている私たちとしては、土を守りながら、その土地の植物を守る視点が大切だと感じます。インドの農家の方々の取り組みを見ていると、とても励まされます。